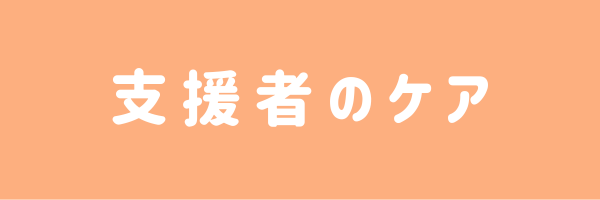
こんにちは、代表の鈴木です。
支援の現場では、「利用者の方のために」と一生懸命になるあまり、自分の気持ちや体調を後回しにしてしまうことがあります。これは相談支援専門員に限らず、介護や看護、教育など、人と向き合う職業に共通する課題だと思います。
支援する人は、「強くなくてはならない」「頼られる側でいなければならない」と無意識に感じてしまいがちです。(本当は違うのですが...これは後述します。)だからこそ、自分が弱音を吐いたり、しんどさを表に出すことにためらいを持つ人も少なくありません。しかし本当は、支援者自身が無理をせず、安心して働き続けられる環境も必要です。
たとえば、支援者が日常の中で抱えるストレスや疲れをそのままにしてしまうと、気づかないうちに「疲弊」や「燃えつき」に近づいていってしまいます。
心や身体がすり減ってしまえば、相手に寄り添う気持ちそのものが薄れてしまうこともあります。そして、それは決して支援者の側の問題だけではありません。
支援する人は強くなくてはならない...ではなく、支援者自身のケアも支援を続けるための必要条件だと捉えることが必要だと思います。
そのためには、支援者自身が安心できる時間を意識して持つこと。気持ちを共有できる仲間がそばにいること。そして実は、「弱さを出してもいい」と思える関係性があること。そうした小さな積み重ねが、支援の質を守り、持続可能にする力になるのです。
当社でも、この点をとても大切にしています。
定期的にミーティングをもち、業務の確認だけでなく、お互いの気持ちや悩みを話し合う時間を設けています。
日常のちょっとした会話を大事にすることも意識していて、「最近どう?」と声をかけ合う習慣が自然と根づいています。
一緒にご飯を食べながらリラックスした雰囲気で、交流する機会を意識的に作る。そうした時間が支援者同士の信頼関係を深め、安心できる空気をつくっています。
支援者もまた、人に支えられて生きている―――その当たり前のことを忘れないようにしたいと思います。
また、「支援者が強くなくてはならない」この点についても考え方をあらためることも必要ではないでしょうか。
言うまでもなく私たちもまた一人の人間です。支援者という立場ではあるのかもしれませんが、「自分一人がその人の人生を背負っている」というある種のおこがましい思いを持たないこと。小さな力しかない一人の人間だからこそ、周囲のいろいろな人の力を借りながら支援を形にしていくことが大切なのではないでしょうか。
支援の仕事は、誰かの人生に寄り添う、とても尊い役割の仕事です。だからこそ、それを担う支援者の心を守り、等身大の自分を受け止め、周りの力も借りること。
そうして初めて本当の意味で持続可能な支援になるのだと思います。
